2012年06月04日
伝教大師・最澄
2012年06月03日
そろそろ ≪ 紫陽花 ≫ が咲き始めて・・・
そろそろ 梅雨入り のニュースが届きそうな季節になってきましたが、近畿地方の平均的な梅雨入り は 「 6月7日 」 頃だそうです。 もう少しで例年並みであれば梅雨入りとなりそうですね。
さて、河原町通をぶらぶらと散歩していると、早くも紫陽花が咲き始めていました。 交通量の多い道沿いとあって、車の熱で付近より暖かいことから、ちょっと早めに咲いたのでしょうか ( 笑 )



いよいよ6月中旬頃から紫陽花が見頃となる季節が到来し、三室戸寺、藤森神社、三千院 など、京都市内あちらこちらの社寺で美しい紫陽花を見ることができます!
6/16(土) らくたび・京都さんぽ でも、境内 約3000株 という 紫陽花 が咲き誇る 大原・三千院 を訪ねる予定をしています。 しかも、専用バス の 送迎付き で大原へ往復して、『 平家物語 』 ゆかりの 寂光院 や、天台声明の根本道場として古い歴史を有する古刹・来迎院 など、奥深い大原の歴史も訪ね歩きます♪
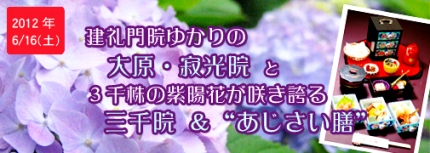
6/16(土) 10:20~16:00
『 平家物語 』 建礼門院ゆかりの大原 ≪ 寂光院 ≫ と
紫陽花が咲き誇る ≪ 三千院 ≫ & ≪ あじさい御膳 ≫
※詳細は、らくたびHP ( こちら ) をご覧ください。
大原まで送迎が付いて、美味しい食事も付いて、さらに講師の解説も付いて、紫陽花を観賞して・・・ と、超盛りだくさんの企画となっていますので、こうご期待ください! 皆さんのご参加をお待ちしています~♪
さて、河原町通をぶらぶらと散歩していると、早くも紫陽花が咲き始めていました。 交通量の多い道沿いとあって、車の熱で付近より暖かいことから、ちょっと早めに咲いたのでしょうか ( 笑 )
いよいよ6月中旬頃から紫陽花が見頃となる季節が到来し、三室戸寺、藤森神社、三千院 など、京都市内あちらこちらの社寺で美しい紫陽花を見ることができます!
6/16(土) らくたび・京都さんぽ でも、境内 約3000株 という 紫陽花 が咲き誇る 大原・三千院 を訪ねる予定をしています。 しかも、専用バス の 送迎付き で大原へ往復して、『 平家物語 』 ゆかりの 寂光院 や、天台声明の根本道場として古い歴史を有する古刹・来迎院 など、奥深い大原の歴史も訪ね歩きます♪
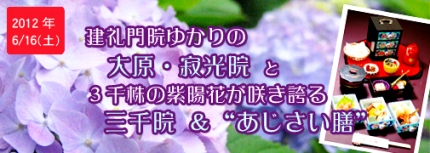
6/16(土) 10:20~16:00
『 平家物語 』 建礼門院ゆかりの大原 ≪ 寂光院 ≫ と
紫陽花が咲き誇る ≪ 三千院 ≫ & ≪ あじさい御膳 ≫
※詳細は、らくたびHP ( こちら ) をご覧ください。
大原まで送迎が付いて、美味しい食事も付いて、さらに講師の解説も付いて、紫陽花を観賞して・・・ と、超盛りだくさんの企画となっていますので、こうご期待ください! 皆さんのご参加をお待ちしています~♪
2012年06月03日
黒船来航
 『 黒船来航 』
『 黒船来航 』嘉永6 ( 1853 ) 年 6月3日、アメリカ から ペリー 率いる 四隻の黒船 ( 蒸気船 ) が相模国浦賀沖 ( 神奈川県 ) に来航し、江戸幕府に米大統領国書を渡して 開国 を迫りました。 このペリー来航によって日本は 幕末 と呼ばれる動乱の時代へ突入しました。
太平の眠りをさます上喜撰
たった四はいで夜も寝れず
高級茶の 上喜撰 ( じょうきせん ) をたった四杯飲んだだけで・・・、つまり 蒸気船 ( 黒船 ) がたった四隻来航しただけで、日本は夜も眠れない大混乱に・・・、という当時の様子を風刺した狂歌です。
武力を背景としたアメリカの圧力的な外交に屈するように幕府は 日米和親条約 を締結し、長い鎖国体制が崩れました。 また、幕府内でも 将軍継嗣問題 から対立が生じ、幕政は転換期を迎えました。
2012年06月02日
≪ 四条京町家、夜は更けて・・・♪ ≫
夜が更けるにつれて、さらに盛り上がり、ついに歌謡ショーが ( 笑 )

世界各国のワインが並んでいます♪

今日は昼間に、町家の衣替えもしましたので、建具がすべて夏のしつらいに変わっています。 これで暑い京都の夏を、涼しくす過ごすことができるでしょう~!

まだまだ、宴は続きます ( 笑 )
世界各国のワインが並んでいます♪
今日は昼間に、町家の衣替えもしましたので、建具がすべて夏のしつらいに変わっています。 これで暑い京都の夏を、涼しくす過ごすことができるでしょう~!
まだまだ、宴は続きます ( 笑 )
2012年06月02日
四条京町家 ≪ 102歳の誕生日 ≫ ピザ・パーティー♪
今宵は、明治43 ( 1910 ) 年 6月4日 に 棟上式 をして建てられた ≪ 四条京町家 ≫ の、102歳の誕生日 を祝う宴会が催されています ( 笑 )
なんと、手作りピザ・パーティー です♪

小さな 石窯 ですが、パワーは充分! 炭火でピザ焼きです♪

ん~♪ 香ばしいピザの香りが漂ってきました ( 笑 )

飲み物はピザに合わせて、シャンパン、赤ワイン、白ワインなど洋酒をメインに、夜更けまで続きそうな四条京町家の誕生会が今も延々と続いています ( 笑 )
なんと、手作りピザ・パーティー です♪
小さな 石窯 ですが、パワーは充分! 炭火でピザ焼きです♪
ん~♪ 香ばしいピザの香りが漂ってきました ( 笑 )
飲み物はピザに合わせて、シャンパン、赤ワイン、白ワインなど洋酒をメインに、夜更けまで続きそうな四条京町家の誕生会が今も延々と続いています ( 笑 )
2012年06月02日
サツキの花が彩る ≪ 智積院庭園 ≫
本日は らくたび ・ 京都さんぽ ( 現地散策講座 ) が開催されまして、京阪・東福寺駅をスタートして・・・
● 辰年ゆかりの 瀧尾神社
● 皇室からも崇敬厚い子授けの 三嶋神社
● 牛若丸の母・常盤御前ゆかりの “ 子そだて薬師 ” を祀る 寶樹寺
● 『 源氏物語 』 にちなむ 夢の浮き橋
● 後白河上皇から厚く信仰された 新熊野神社
● 後白河上皇の菩提を弔う 法住寺
● 後白河天皇陵
● 平清盛が後白河上皇のために法住寺殿に創建した 三十三間堂
・・・と、内容盛りだくさんで京都を巡り ( 笑 )、最後に東山七条に位置する 智積院 ( ちしゃくいん ) と巡ってきました!
智積院庭園 は江戸初期を代表する、書院から眺める 鑑賞式池泉庭園 で、まさに今の季節は サツキ が美しく彩る名庭となります♪

静かに流れ落ちる滝の音も、また趣き深さを感じさせてくれます。

智積院は、元は 豊臣秀吉 が創建した 祥雲禅寺 の跡にあたり、この辺りの庭園は祥雲禅寺の庭園の遺構とされています。

世間の喧騒を忘れて、しばし書院でゆるり ・・・・・ と ♪

最後はほっこりとした時間を過ごしました ( 笑 )
● 辰年ゆかりの 瀧尾神社
● 皇室からも崇敬厚い子授けの 三嶋神社
● 牛若丸の母・常盤御前ゆかりの “ 子そだて薬師 ” を祀る 寶樹寺
● 『 源氏物語 』 にちなむ 夢の浮き橋
● 後白河上皇から厚く信仰された 新熊野神社
● 後白河上皇の菩提を弔う 法住寺
● 後白河天皇陵
● 平清盛が後白河上皇のために法住寺殿に創建した 三十三間堂
・・・と、内容盛りだくさんで京都を巡り ( 笑 )、最後に東山七条に位置する 智積院 ( ちしゃくいん ) と巡ってきました!
智積院庭園 は江戸初期を代表する、書院から眺める 鑑賞式池泉庭園 で、まさに今の季節は サツキ が美しく彩る名庭となります♪
静かに流れ落ちる滝の音も、また趣き深さを感じさせてくれます。
智積院は、元は 豊臣秀吉 が創建した 祥雲禅寺 の跡にあたり、この辺りの庭園は祥雲禅寺の庭園の遺構とされています。
世間の喧騒を忘れて、しばし書院でゆるり ・・・・・ と ♪
最後はほっこりとした時間を過ごしました ( 笑 )
2012年06月02日
本能寺
2012年06月01日
季節の花 ≪ サツキ ≫ が見頃です♪
6月に入り、そろそろ京都にも 梅雨 の足音が聞こえてきそうです。
6月は 美しい花が咲く季節 でもあり、上旬のサツキに始まり、紫陽花 ( あじさい )、花菖蒲 ( はなしょうぶ )、睡蓮 ( すいれん )、沙羅 ( さら : 夏椿 ) など、京都の社寺では美しい花を楽しむことができます。
サツキ

明日の 京都さんぽ では、見頃を迎えている サツキ の花が咲き誇る 智積院庭園 の鑑賞や、NHK大河ドラマ 『 平清盛 』 に登場する 後白河法皇 ゆかりの 新熊野神社 の参拝や、法住寺 の拝観を行います。
明日は天気も良いようなので、ぜひ散策にご参加ください~♪

6/2(土) 13:00~16:00
後白河法皇の菩提を弔う ≪ 法住寺 ≫ と
サツキに彩られる ≪ 智積院 ≫ の名庭鑑賞!
※詳細は、らくたびHP ( こちら ) をご覧ください。
6月は 美しい花が咲く季節 でもあり、上旬のサツキに始まり、紫陽花 ( あじさい )、花菖蒲 ( はなしょうぶ )、睡蓮 ( すいれん )、沙羅 ( さら : 夏椿 ) など、京都の社寺では美しい花を楽しむことができます。
サツキ
明日の 京都さんぽ では、見頃を迎えている サツキ の花が咲き誇る 智積院庭園 の鑑賞や、NHK大河ドラマ 『 平清盛 』 に登場する 後白河法皇 ゆかりの 新熊野神社 の参拝や、法住寺 の拝観を行います。
明日は天気も良いようなので、ぜひ散策にご参加ください~♪

6/2(土) 13:00~16:00
後白河法皇の菩提を弔う ≪ 法住寺 ≫ と
サツキに彩られる ≪ 智積院 ≫ の名庭鑑賞!
※詳細は、らくたびHP ( こちら ) をご覧ください。
2012年06月01日
更衣
季節に応じて衣服や調度をかえることを 「 衣替え 」 といい、現在では一般的に 6月1日 になると 夏の服装 に、10月1日 になると 冬の服装 に衣替えをしています。
「 衣替え 」 は、古くは 『 更衣 』 ( こうい ) といい、平安時代 には 4月1日 と 10月1日 にそれぞれ夏装束・冬装束に改めていました。
また、天皇の着替えに従事した女官の職名 も 「 更衣 」 といい、後に天皇の寝所に奉仕する女官で 「 女御 」 ( にょうご ) に次ぐ女官を 「 更衣 」 と呼ぶようになりました。





